シリーズ労働トラブル防止⑦ 試用期間の誤解

今回は、試用期間についてお話したいと思います。
労働者を雇用した後に、一定期間の試用期間を設ける企業は多いかと思います。
しかし、実はこの試用期間は、大きな労働トラブルに発展する可能性を秘めている制度です。
多くの経営者の方が、試用期間に対して誤った認識を持っているために、安易に労働者を解雇してしまい、その結果大きな労働トラブルに発展するケースというのは非常に多いのです。
今回は、試用期間の注意点について、分かりやすく解説していきたいと思います。
試用期間はお試し期間ではありません

試用期間とは、一般的に採用後、実際の勤務を通して労働者の適性や能力などを評価し、本採用するか否か判断する期間と言われています。
ところで、試用期間は、解雇権留保付労働契約と呼ばれています。
では、なぜこのような名前が付いているか? についてご説明します。
試用期間を設ける場合、労働者を雇用後、その試用期間の勤務状況を見て、正社員として本採用するか否かを判断する形となります。
ですから、試用期間中に労働者の能力や適性を判断して、本採用が不可となる場合は、解雇となります。
従って、解雇権の行使を、試用期間が終了するまで使わないでおく、つまり権利の行使が留保される形となります。
そのため、解雇権留保付労働契約と呼ばれています。
ところで、今ご説明した内容から、「試用期間中に労働者の能力や適性がなければ、解雇できる、解雇しても問題ないわけですね?」と思われる経営者の方が多いのです。
確かに、理論上はそのような形となりますが、たとえ試用期間を設けたとしても、雇用の効力自体は生しています。
つまり、雇用されている労働者を解雇するわけですから、当然客観的、合理的理由が必要となります。
もう少しわかりやすく言いますと、試用期間中に労働者の能力や適性に欠けていると経営者の方が判断しても、その判断に、客観的な妥当性、正当性が必要となります。
つまり、たとえ、試用期間中であったとしても、無条件に労働者を解雇できるわけではないのです。
試用期間中の労働者を解雇するということは、通常の労働者を解雇するよりは、確かに解雇が認められやすいところはありますが、そのハードルは、経営者の方が想像している以上に高いものです。
試用期間のことを、「お試し期間」というように言われる方がいるのですが、決してお試し期間などではありません。
試用期間だからという理由で、安易に労働者を解雇してしまうと、大きな労働トラブルに発展してしまいます。
ところで、現実問題として試用期間中の労働者を解雇せざる得ない場合もあるかと思います。
その場合の注意点ですが、試用期間中の解雇でも、通常の解雇と基本的な考え方は同じとなります。
なお、解雇についての注意点については、こちらの動画で詳しくお話していますので、ぜひご覧になって下さい。
試用期間を設ける場合の注意点

では、実際に試用期間を設ける場合の注意点についてご説明したいと思います。
まず、試用期間の長さですが、試用期間は、どれくらいの長さまで設けることができるか?ということですが、実は、法律には試用期間に関しては定めがありません。
ですから、試用期間の長さについても、本来は会社が自由に決めることができます。
しかし、完全に自由にしてしまうと、労働者保護の観点から支障も出てしまい、実際試用期間に関しては、数多くの裁判が行われてきて、これまでの判例の積み重ねで、試用期間に関しての考え方は、ある程度構築されています。
その考え方からすると、先程もご説明しましたように、試用期間は、解雇権留保付契約と呼ばれていることもあり、あまりにも試用期間が長いのは、労働者の身分が不安定になってしまいますので、一般的には3ヶ月から6ヶ月程度が妥当とされています。
ただし、場合によってはもう少し試用期間必要というケースも考えられます。
しかし、それでもやはり 1年程度が目安かと思います、
あんまりに長い試用期間というものは、裁判等で試用期間そのものが否認されてしまう可能性がありますので、ご注意が必要となります。
次に試用期間中の賃金についてご説明したいと思います。
実は、我が国の法律では、賃金の支払い額についての法律は、最低賃金法しかありません。
つまり、法律の考え方としては、最低賃金以上の金額であれば、どのような支給形態で賃金を支給するかは、会社の自由となります。
従って、試用期間中の賃金は、時給で払って、本採用後月給に変えるというような支給形態でも全く問題ありません。
また、試用期間中は、手当を支給せず基本給だけ支給して、試用期間が終わって本採用になった後、各手当を支給するのも問題ありません。
試用期間と就業規則

次に試用期間におけるノウハウ的なことを、お話したいと思います。
先程ご説明しましたように、試用期間中の解雇が認められるには、試用期間中とは言え、非常にハードルが高いです。
ただし、解雇が、認められ可能性が高くなる方法はいくつかあります。
その1つが、就業規則への規定です。
解雇を巡る裁判においては、解雇するのであれば、その根拠が必要という考え方があります。
その根拠が、就業規則の規定となります。
そして、その規定は、より具体的な方が良いとされています。
これは、どういうことかと言うと、例えば、ある労働者が、窃盗事件を起こして、その労働者を懲戒解雇した場合、その根拠となる就業規則の懲戒規定が、「会社の信用や名誉を著しく損ねた場合、懲戒解雇とする。」という規定と「刑事事件に関与した場合は懲戒解雇とする。」という2つの規定を比べた場合、どちらの規定が、解雇が認められやすくなるかというと、これは後者の方となります。
「刑事事件に関与する。」という、より具体的な規定になっているからです。
つまり、懲戒解雇規定は、より具体的に書くことが、重要なポイントとなります。
実は、これは試用期間中の解雇も同じことが言えます。
少し前の就業規則のテンプレート等では、試用期間終了後、本採用しない規定が、「 能力、資質、健康状態等によって本採用しない場合がある。」という1文だけ終わっているものが結構ありました。
しかし、先程も言いましたように、解雇がより認められやすくなるには、より具体的な規定の方が良いわけですから、試用期間中の解雇についても、なるべく具体的な規定を設けことが、ひとつのポイントとなります。
もちろん、具体的な規定を設けたからといって、解雇が必ず認められるわけではないのですが、ただ認められる可能性が高いのは事実ですので、御社の就業規則を一度確認してみていただければと思います。
なお、試用期間中の就業規則の解雇規定については、以下に例を記載しておきましたのでぜひ参考になさってみて下さい。
【試用期間 解雇規定例】
第〇〇条(試用期間の解約事由)
試用期間中の者が次の各号のいずれかに該当するときは雇用契約を解約する。
① 重要な書類等を指定期日までに提出しないとき
② 正当な理由があることを書面等で証明できない無断遅刻又は無断欠勤をしたとき
③ 正当な理由なく上司の指示に従わなかったとき
④ 就業時間中、業務に専念せず、職場を離れ又は私的な行為を行ったとき
⑤ 健康状態、勤務態度、業務成績、職務能力等が従業員として不適格であると会社が判断したとき
⑥ 会社への提出書類、面接時に述べた内容が事実と異なることが判明したとき。または、業務遂行に支障となる恐れのある既往症や採用の決定に影響する事実を報告しなかったとき
⑦ 第〇〇条第〇項(従業員の遵守事項)に定める遵守事項に違反し、指導するも改善がみられないとき
⑧ その他、前各号に準ずる程度の事由があるとき
⑨ 第〇〇条に定める普通解雇事由に該当したとき
⑩ 第〇〇条に定める懲戒解雇事由に該当したとき
試用期間と解雇予告の誤解について

ここでは、試用期間に関して、経営者の方が誤解する点についてお話したいと思います。
労働者を解雇する場合、労働基準法第20条には、30日以上前に予告をするか平均賃金の30日分以上の支払いを行わなければいけないと定められています。
ただし、この労働基準法第20条には、以下の例外規定が定められています。
①日々雇い入れられる労働者
②2か月以内の期間を定めて使用される労働者
③季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される労働者
④試みの使用期間中の労働者
これは、どういうことかと言いますと、この例外規定に該当する労働者を解雇する場合には、30日以上前に予告する必要もないし、平均賃金の30日分以上の支払いをする必要ありません。
ですから 平均賃金の30日分以上の支払いをせずに、即日解雇することができるわけです。
ここで注意が必要なのが、④の試みの使用期間中の労働者です
試みの使用期間中の労働者を解雇する場合は、今お話しましたように、労働基準法第20条は適用されないこととなります。
ここで注意が必要なのは、この「試みの使用期間中の労働者」の解釈です。
労働基準法における、「試みの使用期間中の労働者」は、雇用後14日以内の労働者のことを言います
ですから、雇用後15日経過した後に、労働者を解雇する場合は、当然 30日以上前に予告するか平均賃金の30日分以上の支払いをするか、しなければいけないわけです。
しかし、多くの経営者の方が、試みの使用期間中の労働者=試用期間中の労働者と誤解してしまっています。
「試みの使用期間中の労働者」の中に、「試」という文字が入っていて、何となく名前が似ているために勘違いされるようです。
そのため、試用期間中の労働者は、労働基準法第20条の適用を受けないので、30日以上前の予告も必要ないし、平均賃金の30日分以上の支払いも必要がない、と思ってしまうのです。
しかし、これは明らかに間違いです。
今ご説明したように、「試みの使用期間中の労働者」は、あくまでの雇用後14日以内の労働者のことですので、たとえ試用期間中の労働者であったとしても、雇用後15日以上経過すれば、「試みの使用期間中の労働者」には該当しません。
つまり、雇用後15日以上経過した労働者を解雇する場合には、その労働者が試用期間中であっても、労働基準法第20条の規定が適用されることとなります。
ここは正しくご理解していただければと思います。
解雇予告の例外に対する誤解
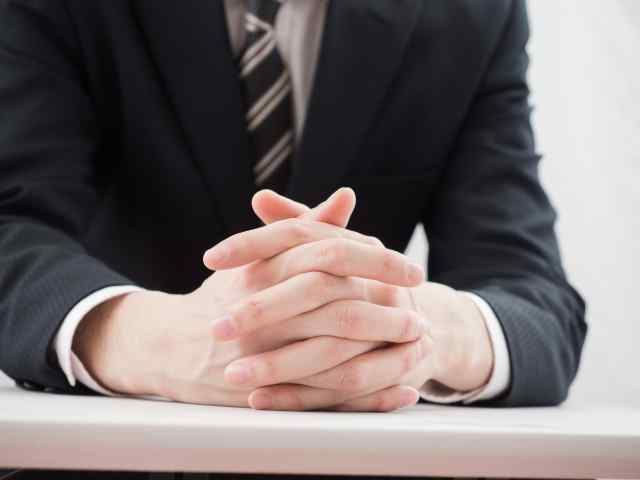
最後に今回のテーマから少し離れますが、1つ重要なことをお話したいと思います。
先程ご説明しましたように、労働基準法第20条の適用の例外に該当する労働者は、
①日々雇い入れられる労働者
②2か月以内の期間を定めて使用される労働者
③季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される労働者
④試みの使用期間中の労働者
となります。
これらの労働者を解雇する場合に関しては、30日以上前に予告する必要もないし、平均賃金の30日分以上の支払いも必要ありません
ただし、 ここで注意しなければいけないのは、これらの労働者は、あくまでも労働基準法第20条が適用されないだけです。
つまり、平均賃金の30日分以上の支払いをしないで、解雇しても労働基準法違反にはならないだけです。
しかし、多くの経営者の方が、この意味を「雇用後14日以内であれば無条件に解雇できる。」と勘違いしてしまっています。
これは、間違いです。
たとえ労働基準法第20条の例外に該当する労働者であったとしても、その労働者を解雇するのであれば、それ相応の理由が必要となってきます。
ですから、たとえ雇用後14日以内の解雇であったとしても、労働者が裁判等で訴えを起こして、不当解雇と認められれば、会社はそれ相応の損害賠償金を支払わなければいけないこととなります。
この点も誤解されている経営者の方が、多いので、今回のテーマのとは少し離れてしまいますが、是非ご注意下さい。
まとめ

試用期間に関しては、多くの経営者の方が、誤解しているところがあります。
試用期間だからといって、無条件で労働者の解雇できるわけではあります。
試用期間は、決してお試し期間ではありません。
試用期間だからといって、安易に労働者を本採用拒否、つまり解雇してしまえば、大きな労働トラブルに発展してしまう可能性がありますので、ぜひご注意下さい。

